 |
|
椎間板は椎骨の椎体間に存在し、線維構造をした線維輪とそれに囲まれた髄核と呼ばれるゼリー状の物質で構成されています。
椎間板の最も大きな機能は椎骨間の運動を円滑にし、外的な衝撃を吸収するクッションの役割を果たしていると考えられています。
|
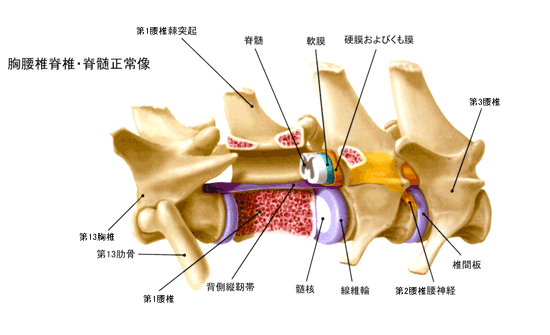 |
 |
椎間板ヘルニアとは、線維輪に亀裂が生じ、髄核が線維輪を押し上げるもしくは破って飛び出してしまう状態を言います。
膨れた(飛び出した)椎間板が、神経などを圧迫する事により、激しい痛みや痺れなどの症状を引き起こします。
椎間板ヘルニアのタイプには大きく2つに分けられます。
①ハンセンⅠ型椎間板ヘルニア(椎間板脱出)
ミニチュアダックスフント、ペキニーズ、トイ・プードル、コッカスパニエル、ウェルシュコーギー、シーズーといった軟骨異栄養性犬種と呼ばれる犬に最も起こりやすい椎間板ヘルニアです。
軟骨異栄養性犬種では2歳までに椎間板の変性が始まり水分がなくなってきます。
そして、中心部分の髄核は硬い物質に変化します。
このような変化が起こると椎間板の衝撃を吸収するクッションの役割が損なわれ、同時に線維輪も弱くなります。
ここに負担がかかると、線維輪が破れ、そこから髄核が飛び出して脊髄を圧迫します。
ハンセンⅠ 型ヘルニアの多くは4~6歳に多く起こり、症状発現は劇的で麻痺や不全麻痺を伴う運動障害を起こすことが多いと言われています。
|
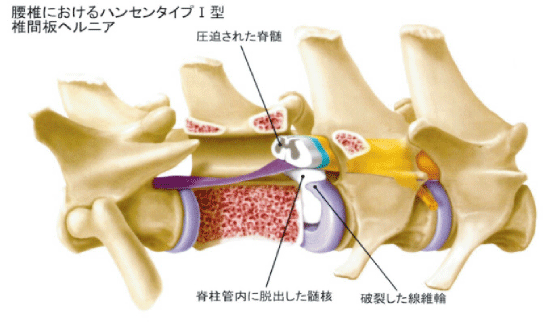 |
|
②ハンセンⅡ型椎間板ヘルニア(椎間板突出)
線維輪の内層が断裂して、その中に移動した髄核が線維輪を押し上げることで脊髄を圧迫するタイプをハンセンⅡ型椎間板ヘルニアと呼びます。
このタイプは柴犬や大型犬(ジャーマンシェパード、ラブラドールレトリーバー、ゴールデンレトリバーによく見られます。
これらの犬種では加齢にともなって、椎間板が変性します。
これは髄核の水分が徐々に減少し、髄核内圧もゆっくり減少するので線維輪を突き破るまで至らないと考えられています。
一般的に慢性的な脊髄圧迫を引き起こします。
|
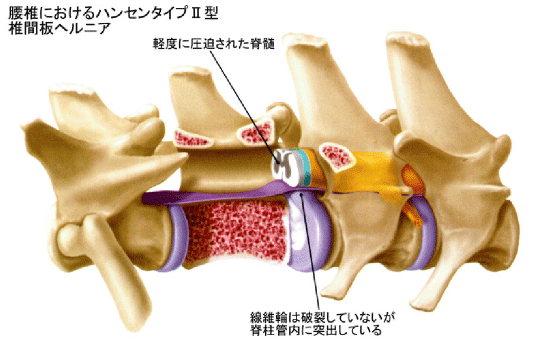 |
 |
|
椎間板ヘルニアの症状はヘルニアの起こった速度、量、部位などにより様々です。
早期に運動失調を認め、つづいて不全麻痺が見られます。
最終的には麻痺、排尿不全、深部痛覚の消失といった症状に至ります。
この過程は数分~数カ月といった時間で進みます。症状の重症度は一般的に5段階に分類されます。
|
|
グレード1
|
軽度の脊髄圧迫のために、脊髄の機能障害がなく、神経学的な異常はないが、脊椎の痛みを生じている状態を言います。
背中を丸める姿勢や階段の昇り降りを躊躇するなど運動したがらないといった症状がみられることがあります。
|
|
グレード2
|
不全麻痺、運動失調を認めます。
歩行は可能であるが、後肢の力が弱いため、ふらつきながら歩く姿が見られます。
足先を引きずるようにして歩くため、爪の背面が磨り減っていることがあります。
|
|
グレード3
|
強い不全麻痺。
後肢の歩行はできませんが、支持することで後肢の起立は可能です。
しかし、歩き出すと前肢だけで進み、後肢は引きずります。
|
|
グレード4
|
麻痺の状態です。
爪や足先の骨を器具を使用して挟むと痛みを訴えます(深部痛覚が存在しています)。
|
|
グレード5
|
後肢麻痺の状態です。
深部痛覚が失われた状態です。
|
|
|
|
深部痛覚が消失するほどの重度の脊髄障害を起こす椎間板ヘルニア(グレード5)の犬のうち
約5~10%で脊髄軟化症に陥ると言われています。
脊髄軟化症を発症した場合、上行性(頭側)にも下行性(尾側)にもすすみ、
呼吸停止を起こして死に至ります。予後は悪く、現在のところ治療法はありません。
|
 |
|
①単純レントゲン検査
椎間板ヘルニアが疑われる患者すべてに実施します。
脊椎のX線検査はその他の疾患(椎間板脊椎炎、外傷や脊椎腫瘍)の区別に役立つことがあります。
単純X線検査だけでは、確定診断が困難ですので、治療として外科手術が考慮される場合、正確な情報(脊髄の圧迫やその脊柱管内における位置)が得るために、必ず脊髄造影検査、CTあるいはMRIによる画像診断を行います。
②脊髄造影レントゲン検査
脊髄造影X線検査とは造影剤をクモ膜下腔へ注入して脊髄の輪郭を描出する検査法です。
獣医学領域では、椎間板ヘルニアによる脊髄圧迫の位置を診断する検査法として主な位置を占めてきたものです。
脊髄造影により86~98%の患者で正確なヘルニア部位を診断できると言われています。
造影剤を使用するため、その副作用が認められることがあります。
造影剤の副作用には痙攣があります。
一般的に腰椎に脊髄針を刺入して造影剤を注入します。
造影剤の注入は、確実にするためレントゲン透視下で行います(図4)。
造影剤の注入後に様々な方向からレントゲン写真を撮影します。
椎間板ヘルニアの場合、典型的には、レントゲンに映し出された造影線が押されたように見えます(図5)。
重症で、脊髄が腫れていたり、脊髄軟化を起こしているなどしている場合は、ヘルニアが起こっている場所の確定が困難なため、CTあるいはMRI検査が必要となります。
③CT
犬の椎間板ヘルニアにおける脊髄造影とCTのヘルニアの位置診断の相対的感度はほぼ同等です。
当院では多列検出器型CT(Multi Detector row CT: MDCT)を導入しており多くの断面を作成することができますので(図6)、優れた評価ができるようになりました。
いくらかの症例で飛び出した髄核を描出できないことでありますので、この場合は脊髄造影と併用して、より確実な診断を行います。
|
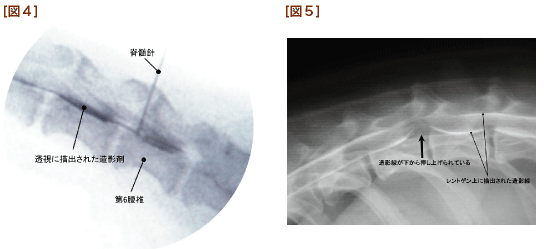 |
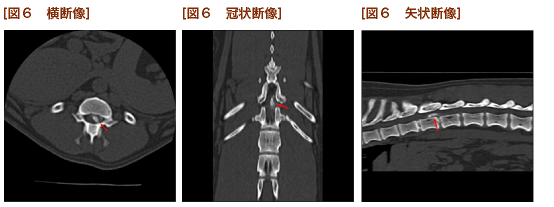 |
 |
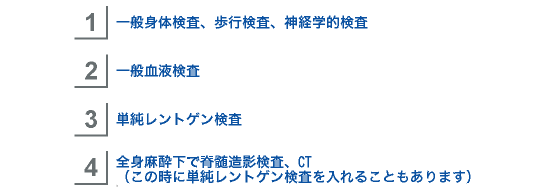 |